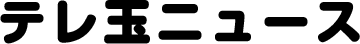桃の節句を前に「人形のまち 岩槻フェア」
桃の節句を前に「人形のまち」として知られる岩槻の魅力をPRする催しが、さいたま市大宮区で開かれています。
会場では、伝統技法「木目込み」で作った招き猫やだるまなどの人形のほか、岩槻の老舗菓子店の時の鐘をかたどったもなかなどのさまざまなスイーツが販売されています。
また、会場の2階では去年に開催された「大阪・関西万博」でさいたま市がひな人形を出展した様子を知ることができるパネルや実際に展示されたすしやだるまの木目込み人形を紹介するコーナーもあります。
「もうすぐひなまつり!人形のまち岩槻フェア」は3月1日午後6時までさいたま市大宮区のまるまるひがしにほんで開かれています。