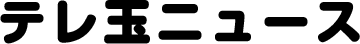大野知事 外務省にトルコとの査証免除一時停止要望
大野知事は、短期滞在の目的であればビザの取得を不要とする「相互査証免除協定」をトルコとの間で一時停止することを求める要望書を外務省に提出しました。
4日は、大野知事が松本尚外務大臣政務官に要望書を手渡しました。
要望書では、「相互査証免除協定」に基づいて入国し、正当な理由がないにも関わらず難民申請を繰り返して外国人が滞在を続け、犯罪行為を行い、住民に不安が広がっていると指摘しています。
さらに、法務省の統計で去年、国籍別で難民申請を複数回行うなどした人が最も多かったトルコに対して協定の一時停止を求めています。
大野知事「(国は)今回真摯に受け止めていただいたと考えている。まずは国の対応を注視したい」