 | 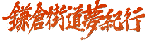 (上道編) (上道編)
鎌倉街道夢紀行〜中道〜の番組内容はこちらです |
| 回 | サブタイトル | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 第一章 鎌倉街道上道 | 鎌倉街道の起点となる鎌倉の鶴岡八幡宮の流鏑馬道から高崎まで、上道(かみつみち)の概要を紹介します。 |
2 |
第二章 高崎 | 高崎城跡より「いざ鎌倉へ」出発。「佐野の渡し」に伝わる悲話や、謡曲「鉢の木」の舞台を訪ねます。 |
3 |
第三章 藤岡 | 七輿山古墳などの古墳群をめぐり、山の中の幻の古道を探訪。 |
4 |
第四章 藤岡・神川 | 藤岡市の街道沿いにある大きな楠や葵八幡を訪ね、神流川を渡って埼玉県神川町へ。八高線に沿った田園風景の中を旅します。 |
| 5 | 第五章 児玉 | 武蔵七党の児玉党が活躍した地。雉岡城址、塙保己一の生家を訪ね、高窓の家(養蚕農家)に立ち寄ります。 |
| 6 | 第六章 美里 | ここで作られた瓦が鎌倉に運ばれ、三大寺院のひとつ永福寺の修復に使われました。街道を使って運ばれたのか、それとも舟運を使ったのか、謎となっています。 |
| 7 | 第七章 寄居・花園 | 戦国時代の城下町だった寄居と花園。鎌倉街道に沿って、鉢形城、用土城などの城跡があります。 |
| 8 | 第八章 寄居・川本 | 「赤浜の渡し」で荒川を渡ると、畠山重忠生誕の地である川本町に入ります。重忠ゆかりの場所を訪ね、藪の中に残る街道の跡をたどります。 |
| 9 | 第九章 小川 | 和紙の里として知られる小川町。田園から林の中へと、よく残された街道の跡をめぐります。戦国時代の軍事的に重要な拠点であった杉山城跡などを訪ねます。 |
| 10 | 第十章 嵐山 | 京都の嵐山に似ていることから名付けられたこの地は、木曽義仲の生まれた地であり、畠山重忠の居城、菅谷館のあった所です。鎌倉武士の鑑と言われた重忠の最期を語ります。 |
| 11 | 第十一章 笛吹峠 | 鎌倉街道上道最大の難所であった笛吹峠。なにか物語がありそうな名前です。旅人はこれまでの道のりを思い出しながら、ここで笛を吹きます。 |
| 12 | 第十二章 鳩山 | 笛吹峠から南へ向かい、街道端沼、羽黒堂を通って、鳩山中学校へ。ここには、かつて校舎の下に街道の跡があったそうです。そして街道杉を通って越辺川へ。旅人は地元の人に話を聞いたり、道標を手がかりに街道の跡を探します。 |
| 13 | 第十三章 毛呂山 | 日本最古の流鏑馬(やぶさめ)で知られる毛呂山町。ここには往時の姿そのままの街道が残っています。越辺川を渡り、苦林野古戦場から歩きはじめ、今も残る貴重な街道跡を歩きます。 |
| 14 | 第十四章 日高 | 日高に入った街道は数々のゆかりの地を通り、北条、足利の戦地・女影から木曽義仲の子、義高最期の地、入間川・八丁の渡しへと続きます。 |
| 15 | 第十五章 狭山 | お茶で有名な狭山。ここは新田義貞ゆかりの場所が数多く残っています。城山砦跡より入間川を渡り三ツ木原古戦場、堀兼の井へと向かいます。 |
| 16 | 第十六章 所沢 | 新田義貞の三男、義宗は、武蔵野合戦で足利尊氏に敗れたあと、再起を期して所沢市内の薬王寺に隠れ住んでいました。いま、その寺にはこのような句碑がたっています。「武蔵野にらちなく老いし柳かな」 |
| 17 | 第十七章 小手指 | 所沢の西にある小手指ヶ原古戦場。鎌倉をめざして南下してきた新田義貞が鎌倉勢と緒戦を戦った場所です。群馬を出発したときはわずか150騎ほどだった軍勢ですが、この地に達したときは20万の大軍になっていたそうです。 |
| 18 | 第十八章 東村山 | 八国山にある将軍塚には、新田義貞が家臣の供養のために建てた「元弘の板碑」の所在碑があります。この板碑が保存されている寺のご住職に、義貞の人間像を伺います。そして、国宝に指定されている美しい正福寺地蔵堂を訪ねます。 |
| 19 | 第十九章 国分寺 | 国分寺の恋ヶ窪には、鎌倉街道にまつわる悲恋物語が伝わっています。その主人公はあの畠山重忠。重忠はこの地の美しい遊女、夙妻(あさづま)太夫とただならぬ仲となりますが… 熊野神社にはこのような歌碑が立っています。「朽ち果てぬ名のみ残れる恋ヶ窪 今はたとうもちぎりならずや」 |
| 20 | 第二十章 府中 | 古代、武蔵の国の国府がおかれた府中。多摩川の分倍河原は、鎌倉に攻めいる新田義貞の決戦の舞台となった所です。市内の善明寺には、国分寺の恋ヶ窪で紹介した畠山重忠と夙妻太夫の悲しいロマンスの後日談を伝える仏像がありました。 |
| 21 | 第二十一章 町田 | 町田市郊外の山中には、およそ1キロにわたる静かな街道跡があります。その先の七国山には、新田義貞が鎌倉攻めのときに軍馬に水を飲ませたという「鎌倉井戸」が残っています。 |
| 22 | 第二十二章 横浜 | 横浜に入った鎌倉街道上道は、江戸時代、境川沿いに商家が立ち並んだ江戸柳明(えどやなみょう)呼ばれる街を通ってゆきます。 |
| 23 | 第二十三章 横浜・藤沢 | 藤沢にある時宗の総本山、遊行寺。新田義貞が鎌倉に迫り、世の中が騒然としたときにも、この地は戦火がおよばず、両陣営の兵がここで念仏を唱えたそうです。 |
| 24 | 第二十四章 鎌倉(前編) | 新田軍は、化粧坂(けわいざか)、巨福呂坂(こぶくろざか)、極楽寺坂の3つの入り口から鎌倉に攻め込みます。しかし、本隊は化粧坂で北条軍の堅い守りに苦戦、極楽寺坂でも勇将を失います。そして義貞は起死回生の策として、極楽寺坂の北条軍の背後を突くため、化粧坂から尾根伝いに軍勢を差し向けるのです… そのときに通ったとされるのが大仏坂の切り通し。これまで歩いてきた街道の中でもとくに険しい切り通しです。 |
| 25 | 第二十五章 鎌倉(後編) | 鎌倉・稲村ヶ崎の海にたどりついた旅人は、街道ゆかりの3人の人物の足跡をたどります。その一人は、「龍の口の法難」によって佐渡流罪となった日蓮。もう一人は、謀反の疑いをかけられ、二俣川で戦った畠山重忠。そして最後の一人は、街道を駆け抜けた新田義貞。 義貞は、黄金の太刀を海神に献じ、波が引いた時に海岸から一気に鎌倉に攻め込み、幕府を滅亡させたのです。 |
| 26 | 最終章 鎌倉街道上道 | いよいよ番組の最終回。これまで歩いてきた道を振り返ります。 |