 | 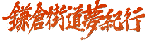 〜中道〜 〜中道〜
鎌倉街道夢紀行(上道編)の番組内容はこちらです |
| 回 | サブタイトル | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 第一章 鎌倉 | ふたたび鎌倉を訪れた旅人は、心落ち着く場所を訪ね、新しい旅に思いをめぐらせます。そして、秋雨にけむる鶴岡八幡宮の大イチョウの下から、また長い旅が始まりました。 |
| 2 | 第二章 横浜・南部 | 中道の基点となる水堰橋を出発し、道標を手がかりに街道跡をたどります。 高台にある公園の中には、往時そのままの街道の姿が残されていました。 |
| 3 | 第三章 横浜・北部 | 鎌倉武士の鑑といわれた畠山重忠。その終焉の地である横浜の鶴ヶ峰を通り、街道は住宅地へ入ります。源義家や頼朝の伝承が残る白根神社を抜け、街道は町境を真っ直ぐに北へと向かいます。 |
| 4 | 第四章 川崎 | 街道は横浜の荏田から川崎に入り、大山街道をなぞるように進みます。 途中にある剣神社には、この街道が奥州と鎌倉とを結んでいることをうかがわせる、剣にまつわる伝説が伝わっています。庚申塔などを頼りに道を進むと、やがて多摩川の二子の渡しに行き着きます。 |
| 5 | 第五章 東京・西回り その1 | 多摩川を渡ると、東京への入り口にあるのが兵庫島。新田義興最後の地、矢口の渡しの上流にあります。ここから街道は西回りと東回りに分かれますが、今回は西回りコースを歩きます。街道は世田谷に入り、源義家ゆかりの地、弦巻(つるまき)を訪ねます。そして、かつては世田谷城の一角にあったという豪徳寺で、旅人は静寂のひとときを楽しみます。 |
| 6 | 第六章 東京・西回り その2 | 杉並区にある大宮八幡神社。厳かな雰囲気が漂う、源氏ゆかりのこの神社を出発した旅人は、中野区の多田神社、十貫坂を過ぎ、もみじ山公園の前を進みます。そして新井薬師前駅近くの踏切を渡り、住宅街の中の細い坂を下って行くと、やがて江古田公園に至ります。いまは静かな佇まいを見せるこの場所は、かつて太田道灌の一大決戦の舞台となった江古田ヶ原沼袋古戦場跡なのです。 |
| 7 | 第七章 東京・東回り その1 | 多摩川の兵庫島に戻った旅人は、今度は東回りのルートで都心部を探索します。街道は、ぬかるみで倒れた愛馬を頼朝が弔ったという伝説が伝わる芦毛塚から駒繋神社を経て、目切坂から代官山の猿楽塚に至ります。そして渋谷駅を左手にみて、青山に入り、原宿の表参道を横切ります。 |
| 8 | 第八章 東京・東回り その2 | 新宿御苑前を出発した旅人は、西向天神にある太田道灌ゆかりの「紅皿の碑」を訪ねます。ここには、蓑を借りきた道灌に、村の娘が山吹の一枝を差し出したという「山吹の里伝説」が伝わっています。街道は高田馬場から、面影橋を経て、池袋のサンシャインビルを望みながら高いビルの合間を抜けて進みます。 |
| 9 | 第九章 川口・鳩ヶ谷 | 荒川を渡り、埼玉へ。源義経の伝記である「義経記」には、治承4年1180年、頼朝の挙兵に応じて奥州から駆けつけた義経が「武蔵国足立郡こかわぐちを過ぎる時、従う軍勢は85騎」と記されています。当時すでに川口は奥州への街道の要所であったことがわかります。往時をしのばせる鎌倉橋の碑から鳩ヶ谷へと向かいます。 |
| 10 | 第十章 川口・浦和 |
川口を過ぎ、浦和の大門に入ると、雑木林に囲まれてひっそりと残る街道を見つけることができました。旅人は、道端の道標をなんとか読もうと試みますが・・・ 大門は江戸時代、日光御成道の宿場として栄えた所で、大門宿本陣と脇本陣の表門がそろって残されています。旅人は、時がとまったかのような空間が広がる大門神社を後に、北へ向かいます。 |
| 11 | 第十一章 岩槻・前編 | 人形の町として知られる岩槻市に入ると、街道は2つのルートにわかれます。旅人は、ゆったりとした田園風景を楽しみながら岩槻城址に向かいます。この地に太田道灌が築城した岩槻城は、関東では小田原城に次ぐ規模だったそうですが、いまでは静かな公園になっています。かつて大手門があったあたりには、江戸にまで音が届いたという「時の鐘」が残されていました。 |
| 12 | 第十二章 岩槻・後編 | 前回に引き続き、岩槻市を探索。今回は東側のコースをたどって慈恩寺に向かいます。元荒川の近くにある金剛院を出発した旅人は、弁慶が残していったという十一面観音が安置されている大光寺を訪れます。そして、岩槻市と春日部市の境である川堤に残る街道跡を歩きます。その先の慈恩寺は坂東十二番の札所として知られる名刹です。 |
| 13 | 第十三章 宮代・杉戸 | 鎌倉街道中道は日光御成街道に合流して北へ進みます。宮代町須賀にある古寺、真蔵院の仁王門の前から伸びる細い道が鎌倉街道といわれています。この道は古利根川を高野の渡しで渡ります。この渡しは武蔵野の国と下総の国の境でもあり、高野の地名は「義経記」にも登場しています。川を渡った旅人は、杉戸町に残る「西行法師見返りの松」を訪ねます。 |
| 14 | 第十四章 栗橋 | 街道は幸手から栗橋に入ります。利根川に臨む栗橋の宿にはかつて関所がありました。栗橋駅の東には「静御前の墓」があります。奥州平泉に逃れた義経を追って、このあたりまできた静御前は、義経の死の知らせを聞き尼となりますが、気も心も弱りはて、ついにこの地で帰らぬ人となったという言い伝えが残っています。 |
| 15 | 第十五章 古河 | 利根川を渡り、街道は茨城県総和町に至ります。この地にも静御前の伝承が残っていました。旅人はさらに北の古河市へと入り、足利氏の末裔の物語が残る古河公方の館跡を訪ねます。そして、以仁王を奉じて平家追討のために挙兵した源三位頼政をまつる頼政神社へと向かいます。 |
| 16 | 第十六章 野木・小山 | 栃木県に入った鎌倉街道の探索は、野木町の野木神社から始めます。この神社付近を何本かの古道が通っていたといわれます。野木町では2通りの街道跡を訪ねますが、そのひとつは広大な景色が広がる思川(おもいがわ)の河岸段丘上の尾根道として残っていました。やがて街道は小山市の間々田八幡宮に至ります。平将門の乱を平定した藤原秀郷が戦勝祈願をした神社といわれ、源頼朝も奥州での戦勝を祈願したと伝えられています。 |
| 17 | 第十七章 小山 | 小山市にある千駄塚古墳は、このあたりを通った奥州の商人とこの地の富豪との千駄の荷物をめぐる賭け事が、その名前の由来となっています。この古墳から北へ向かうと藤原秀郷が社領を寄進したという安房神社がありました。そのわきの林の中には「鎌倉道」とかかれた標柱の立つ、ひっそりとした細い道があります。やがて街道は、中世に栄えた小山氏の居城であった小山城址と小山氏の菩提寺、天翁院に至ります。 |
| 18 | 第十八章 宇都宮 | 下野国の中心、宇都宮の街道探索は、南の入り口あたりにそびえる大ケヤキからはじまります。樹齢800年といわれるこの大木、鎌倉時代から旅人を見守っていたのかもしれません。宇都宮には義経の後を追った静御前にまつわる伝説がいくつか残っています。そのひとつは、供をしていた亀井六郎が地面に槍を突き刺すと湧き出たという「亀井の水」。そして、春に美しい花を咲かせる、静桜と呼ばれる桜の木も、静御前の悲しい物語を伝えています。 |
| 19 | 第十九章 河内・氏家 | 河内町から、鬼怒川を越え、氏家町までを探索します。 河内町にある製紙工場の敷地内には、街道を示す碑が残っています。 さらに北へ向かうと下ヶ橋の宿があります。この地にかつてあった養膳寺には かつて頼朝のもとへ駆けつけた義経がここで休んだという言い伝えが 残っています。やがて鬼怒川を越えて氏家町に入ると、舟玉神社があります。 このあたりは中世以降、舟運で栄えた場所といわれます。 |
| 20 | 第二十章 喜連川・大田原 | 今は温泉の町として賑わう喜連川町ですが、かつては奥州街道の 宿場町として栄えていました。古河公方・足利氏の流れをくむ喜連川氏の 城下町です。ここから関街道と呼ばれる道を北へ進むと山道を越えて やがて大田原市に入ります。ここにある玄性寺には源平合戦で華々しい武芸を見せた 弓の名手、那須与一の墓があります。屋島の戦いの時、平家方の船に立てられた 扇の的を見事に射抜いたエピソードは有名です。 大田原もまた奥州街道の交通の要衝で、古い道標なども残っています。 |
| 21 | 第二十一章 那須 | 黒羽町から那須町を通り、白河の関に向かう道は義経街道とも呼ばれ、奥州から兄・頼朝のもとへ馳せ参じた義経ゆかりの場所が残っています。義経の愛馬の病が治るように常陸坊海尊が祈願したという「馬頭観音堂」、一行が休息したという「御幣神社」、愛馬の足跡とされる「沓石」などが、義経伝説を今に伝えていました。そして、下野と陸奥の国境にある「追分明神」もまた、義経が平家討伐の祈願をしたという伝承の残る神社です。 |
| 22 | 第二十二章 白河 | 古代より陸奥の国の入り口だった白河の関。 源頼朝もここを通って奥州へ攻め込んだとされます。 また、この地は歌枕としても知られ、能因法師らの 和歌に読み込まれてきました。 関の近くには、この地を治めていた信夫庄司・佐藤元治が、 息子の佐藤継信、忠信兄弟を源義経に従わせたときに、 ここまで見送り、「お前たちの忠義が本物ならばこの杖は生きつくだろう」 といって桜の杖をさしたという「庄司戻しの桜」があります。 |
| 23 | 第二十三章 福島 | 文治5年(1189年)、奥州の藤原氏討伐に向かった 源頼朝は白河の関を越えて、陸奥に入り、現在の福島県の 厚樫山(国見山)付近で初めて藤原泰衡の軍勢と戦いました。 泰衡軍は山頂から阿武隈川まで堀をつくり、頼朝軍を 迎え討ちましたが、この時までに10万騎にも増えたと いわれる頼朝軍を前に戦いは3日間で終わり、厚樫山の砦は 陥落してしまうのです。 現在も残る堀の跡が、激しい戦いの様子を物語っています。 |
| 24 | 第二十四章 宮城 | 宮城県にある多賀城址は、中世に国府が置かれた 場所で、源頼義、義家もここで北の地を治めました。 城址に残る多賀城碑は、天平年間に建てられたものといわれ、 平泉に進軍する頼朝は、この古碑を見て歌を詠んでいます。 この地から北に進むと栗駒町に入り、「義経北行伝説」にまつわる、 義経の墓と伝えられる五輪塔と石碑のある「判官森」があります。 そして、栗駒町にある栗原寺は、迎えにきた藤原秀衡が義経と 初めて対面した場所だとされます。 |
| 25 | 第二十五章 平泉 | 文治5年(1189年)8月、頼朝は厳美渓を越えて平泉へ進軍します。 藤原泰衡はすでに北に逃走しており、頼朝は無血入城を果たすのです。 平泉の町は、清衡、基衡、秀衡の藤原氏3代100年にわたって、 大規模な仏教都市が作られていました。清衡は戦乱のない世の中の 到来をねがって中尊寺を再興し、基衡は中尊寺をしのぐ大伽藍の造立に 着手しました。今は大泉池が往時の規模を伝える毛越寺です。 そして、北上川を見下ろす山の上に、源義経最後の地となった義経堂があります。 |
| 26 | 最終章 鎌倉街道中道 | 秋雨にけむる鎌倉の鶴岡八幡宮からはじまった今回の 鎌倉街道中道の旅。 源頼朝の奥州攻めの道すじをたどりながら、旅人は平泉まで やってきました。最終回では、旅人はピアニストの姿に戻って、 これまでの旅の思い出を振り返りながら、平泉郷土館のピアノを奏でます。 |